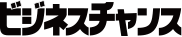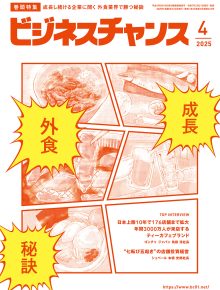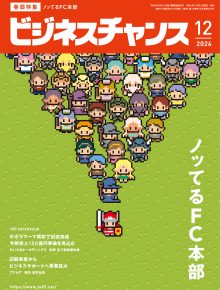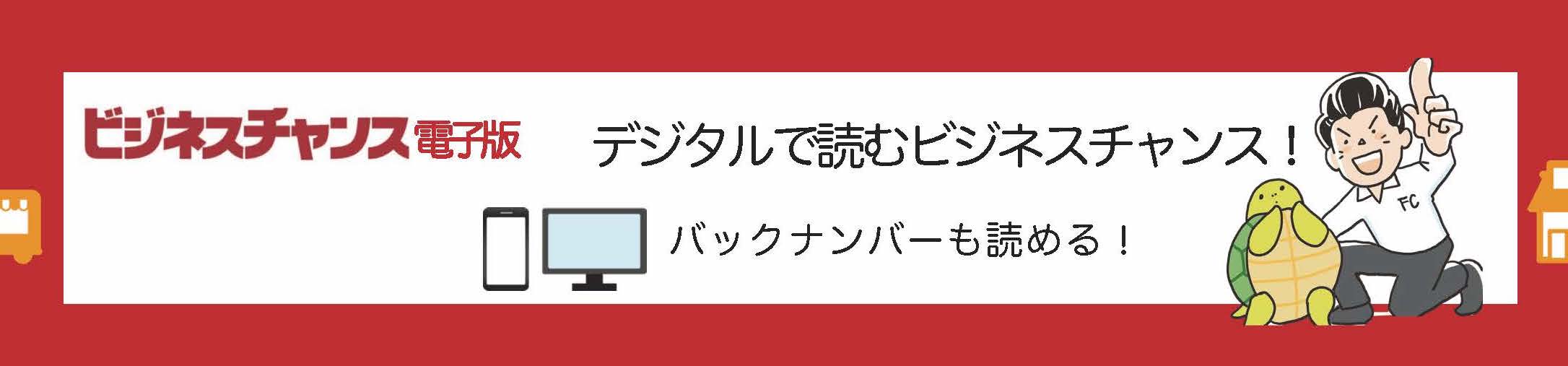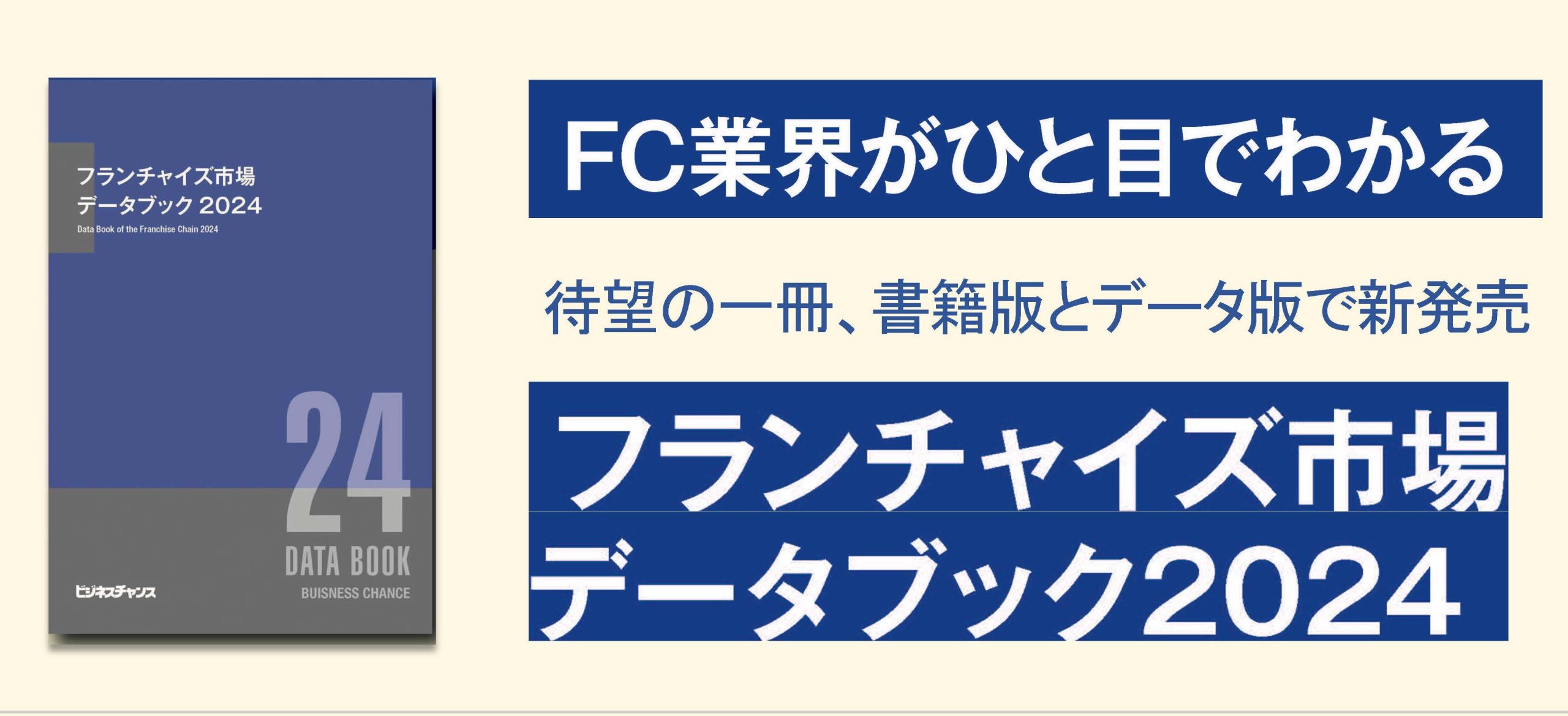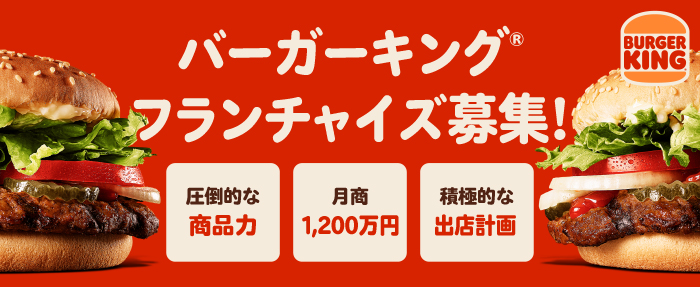【ゴンチャ ジャパン】日本上陸10年で176店舗まで拡大(後編)
公開日:2025.02.26
最終更新日:2025.02.26
※以下はビジネスチャンス2025年4月号から抜粋した記事で、内容は取材時の情報です。
多様な出店立地を持つFCモデル
同社は、飲料市場の中では未成熟のティーカフェ市場のシェア拡大を実現するため、まずは400店舗体制を目指す。店舗数拡大において重要な鍵を握るのがFCだ。ティーの提供がメインとなるゴンチャは、一般的な飲食業態と比較して厨房設備が少なく、10坪から出店可能となっている。また、近年は知名度が向上したことで、空中階など人流が少ない場所でも高売上を叩き出しているという。
イートイン併設が大半 一部テイクアウト専門店も
──ゴンチャの店舗は6~30坪とバラエティ豊富です。
角田 出店形態は大きく2つで、イートインを充実させた「ティーカフェ」と10席未満の「ティースタンド」があります。現状は店舗全体の6割がティーカフェです。出店立地はSCが大半で、そのほか路面店や駅ナカ、アウトレットや空港、サービスエリアに出店しています。
──出店の際に重視することは何ですか。
角田 立地ですね。ゴンチャは通行量と売上が直結するところがあり、通行量の多い店舗では月商約2000万円を叩き出すほどです。一方、リテールの実施などでゴンチャの知名度が上がったことで、新宿のミロード4階や梅田のLINKS 4階などの空中階の売上もかなり上がっています。
──立地による直営とFCの棲み分けはありますか。
角田 ないですね。直営は基本的に関東と近畿のみです。唯一、直営とFCの分かれ目があるとすれば賃料比率で、FCオーナー様からみてチャレンジングになる物件は直営で出していきます。賃料比率15%くらいになると我々が出店して、そこで我々がしっかり数字を作れれば、オーナー様の安心感に繫がると思います。
──初期投資を教えてください。
角田 店舗取得費を除くトータルの初期投資は、3500~4000万円となります。内訳は加盟金200万円、保証金300万円、出店サポート費30万円、設計管理工事費3000万円です。
──収益モデルは。
角田 月商750万円に対して、償却前利益は90万円(12%)です。費用の内訳は、原価218万円(29%)、人件費165万円(22%)、家賃90万円(12%)、ロイヤリティ22.55万円(3%)、広告分担金26.2万円(3.5%)、荷造運搬費26.2万円(3.5%)、その他経費112.1万円(15%)となっています。投資回収期間は40カ月以内を見込んでいます。
既存オーナーの増店加速 中期で400店舗を見据える
──出店に関して、現状ではどこまで見えていますか。
角田 28~30年に400店舗はいけるかなと。今のお客様の支持状況を見ていると、それくらいのニーズはあると思います。
──現在は176店舗体制で、直営比率が約2割となっています。400店舗体制になった場合、直営とFC比率はどうするお考えですか。
角田 基本的に直営は全体の2割程度を想定しています。直営の役割として第一に、ブランドを作っていくためのチャレンジがあります。そのほかにも複数店を経営するためのSVや店長の配置、社員とアルバイトの割合などオペレーションのスタンダードを築き、加盟店に共有していきたいと思います。
ただ、400店舗規模になったら直営比率を少し下げて直営は60店舗くらいを想定しています。今は有難いことにFCオーナー様の出店意欲が高く、出店がしやすい環境となっています。
──現在のオーナー数と属性を教えてください。
角田 オーナー様は40社で、飲食業をされている方が多いですね。運営店舗数は3~4店舗がボリュームゾーンで、最も多いオーナー様で10店舗以上を運営されています。
スタッフの充実度を高める取り組み
ゴンチャのメイン顧客は10~20代の若年女性で、学生が特に多い。また、スタッフの年代も顧客層と近しく、現在はクルー(アルバイトスタッフ)の9割がゴンチャ利用者となっている。そのため採用に強く、求人媒体に掲載しなくても募集人数の3倍ほどの人材が集まるという。また、同社は現場で働くスタッフの充実度を重視しており、スタッフに向けた取り組みを多数実施。選ばれる職場づくりをする一方で、スタッフからもブランドファンを創出している。
スタッフこそファンナンバーワン 社会人以降も繫がる仕組みづくり
──ゴンチャは顧客層が若いので、高いLTV(顧客生涯価値)が期待できそうです。
角田 上陸当初のペルソナは15~25歳の女性でした。そして上陸から10年経ち、現在は15~35歳まで広がりました。お茶の強みは産まれたての赤ちゃんからお年寄りまで、あらゆる場面で飲めることです。だからこそ、社会人になった後にいかにファンのままで居続けてもらうかが重要です。今後はファンの方にもっと楽しんでもらえるようなプログラムの導入も検討しています。
──メイン顧客である若年女性向けの集客施策として学割がありますが、社会人向けの施策はありますか。
角田 ご利用いただいているお客様を第一に考える一方で、働いているクルーこそファンナンバーワンだと思っています。そのため、クルーには全店舗で商品が2割引となるモバイル版のクルーパスをお渡ししています。これは永久に使えるので、OG・OBになってもゴンチャと繋がっていただけることになります。
──ゴンチャは顧客層とスタッフの年代が近いため、採用も強そうです。
角田 今働いているクルーの9割がゴンチャを利用したお客様です。クルーの募集をかけると3倍くらいの応募があります。横須賀でも約150人の応募実績があり、平均で100人以上は来ますね。
──新規オープンの際は、求人媒体を使うのでしょうか。
角田 使わない場合が多いです。基本はサイトや公式LINE、ポスターで求人募集をしています。ただ、サービスエリアなどアクセスしにくい立地や出店が決まってからオープンまでの期間が短い場合には、求人媒体を使います。
──多くの応募があれば、優秀な人材を採れるメリットがあります。
角田 3人を募集する中で6人の応募があれば、その店舗にフィットしそうな人を採用できます。そのため、ゴンチャで働いている方々は本当に優秀で、逆に店長にプレッシャーがかかる感じがあります。
スタッフの声を取り入れ メニュー企画イベントを実施
──店舗オペレーションの効率化のために実施していることはありますか。
角田 効率的に商品を作るために分業体制をとっています。注文商品ラベルを貼るラベラー、ドリンクを作るブレンダー、お会計をするPOS、お渡しの4つのポジションがあり、当日割り当てられたポジションに集中してもらう形です。それぞれがお客様のためにチームワークで商品を仕上げている感じがして、すごく楽しいです。
実は先日、僕もお店に入って分業の中の渡す係をやりました。クルーの方からすると僕はアマチュアですので色々と気にかけてくれたり、サポートに入ってくれました。やっていて部活っぽいなぁと思いましたし、楽しいんですよね。アルバイトの方がハマる理由も分かります。
──角田社長も臨店するのですね。
角田 サブウェイ時代から臨店は結構しており、よく半パン・Tシャツで行きます。お客様に楽しんでいただくためには、まずは現場で働くクルーが充実した時間を過ごしていないといけません。そのために、クルーに対する取り組みを色々やっています。たとえば、昨年のクリスマスは蝶ネクタイをしてみたり、サンタの帽子を送ってみたり、Tシャツを変更したりしました。
また、クルーに「どういうことをやったら盛り上がるの?」と聞いてみたら、「メニューを考えてみたい」という声が結構あったので、クルー企画メニューをやることにしました。昨年は、「ゴンチャクルーチャンピオンシップ2024」と題してクルー企画メニューを販売し、大い盛り上がりました。

ティーカフェ店舗

ティースタンド店舗
ティーカフェの定着を目指す
コーヒーチェーンが大半を占めるカフェ市場において、同社が目指すのはティーカフェのシェア拡大だ。現状はカフェ市場の中の1割にも満たないが、同ブランドを広めることでティーカフェの定着を狙う。そうした中で、ゴンチャは独自の取り組みにより既存のカフェチェーンとの差別化を図っている。仕事や勉強をするサードプレイスとは対照的な「おしゃべり需要」に焦点を当てた1.5人席が話題となり、若年層のコミュニケーションの場として根付き始めている。
比較的新しいティーカフェ業態 潜在需要の高い茶の可能性
──ゴンチャが属するティーカフェ市場は、現状でどのくらいの規模があるのでしょうか。
角田 まず、お茶全体の市場規模は1兆円以上と言われており、コーヒー市場と一緒かそれより大きいとされています。また、カフェ市場は7000億円くらいありますが、現状はコーヒーカフェが大半を占めており、ティーカフェはまだ1割にも至っていません。
ティーカフェに含まれるブランドは当店のほか、ナナズグリーンティーさんやアフタヌーンティーさんが代表的ですが、店舗数ベースではそんなに大きくはありませんでした。そういう意味でいうと、ティーカフェ市場の中ではゴンチャが単体で店舗数を増やしている状態です。しかし、コーヒーとの比較で言うと、ティーカフェ市場はまだまだ規模が小さいため、成長余地が大いにあると思っています。
──カフェ市場にはコーヒーやティー、さらにはフラペチーノやタピオカといったデザートドリンクといった分類があります。
角田 我々がカフェ市場の中で一番狙いやすいのはデザートドリンク市場で、その市場規模は約3000億円と言われています。ゴンチャの場合はトッピングや季節限定商品がデザートドリンク市場での競争力となり、メインのターゲットになり得ると考えています。
──年間来店者数はどのくらいですか。
角田 昨年は約3000万人でした。我々は、店舗数よりもどれだけ多くの方にご利用いただいたかを重視しています。1店舗で1日500人、それが170店舗で×365日。こうした積み重ねだと思っています。そのため、チェーン全体の月間来店者数は社内全員が把握しています。

昨年実施の「ゴンチャ クルーチャンピオンシップ 2024」
ゴンチャ体験の価値を高めるセルフオーダー導入を促進
──先ほどティーカフェというお話がありましたが、カフェとして居心地のよい空間を演出するため、近年は友人とのおしゃべりに適した仕切りの付いた狭めのシート「1.5人席」の導入が進んでいます。
角田 1.5人席は21年から開始して、現在5店舗で導入されています。
──この取り組みは他社と差別化できる一方で、回転率が下がってしまう可能性もあります。そこのリスクヘッジはどうしていますか。
角田 席の有る無しがゴンチャ利用の決め手ではないため、特に何かしているわけではありません。もともと持ち歩きで飲めるのがゴンチャの強みの1つですので、席が空いていなければ近くのベンチで座って飲んでいるようなイメージです。決して、席を回転して儲けようということではありません。
──お客さんの平均滞在時間はどのくらいですか。
角田 感覚値で15~30分ですかね。1時間居たら相当長い方です。おしゃべりがメインなので勉強する人がいないですし、PCを開く人もいない。その点、スターバックスさんとは雰囲気が全然違います。おしゃべりをしている方が、よっぽど回転率が高いと思います。
──最近はセルフオーダーにも注力されています。
角田 セルフオーダーはモバイルとキオスク端末の2パターンで進めており、モバイルは全店、キオスク端末は全体の3分の1程度が導入済みです。もちろん、ゴンチャらしい接客も大事にしていきますが、ユーザーのニーズを考えたときにストレスなくスムーズに買える体験の方が大きいと思っています。
お客様との接点は商品をお渡しする際に作れるので、そちらに注力します。たとえば、新幹線の切符を買うのにどんなに丁寧にやってもらってもわざわざ緑の窓口に行きたいと思わないじゃないですか。体験価値で考えるといかに自分の都合に合わせて気を使わずに、柔軟に予約が取れるかだと思うので、当店もストレスフリーな購入方法として将来的には全店でキオスク端末を導入する予定です。
──御社の競合として、最近はスターバックスが手掛けるティーブランド「TEAVANA」の存在や、「MIXUE」や「COTTICOFFEE」といった中国発祥のティーブランドの上陸が相次ぎました。
角田 競争があるのは当然ですし、消費者としても選択肢が多い方がよいと思っています。その中で、お茶のクオリティや楽しみ方、店舗を含め、消費者がする一連の体験の中で我々が一番でありたいです。そのため、競合を見るよりも我々がやりたいこと、つまり消費者にとって価値のあるゴンチャ体験を作ることにフォーカスしていきます。
──総じて、他社が参入してくることに関してはポジティブなお考えですか。
角田 ポジティブです。1社だけでティーカフェを作るというよりは、色んなブランドがある中で1番でいたいです。市場もコロナ以降は、元気のあるブランドがない状態です。そういう意味では、ほかのブランドが元気になって、市場が活性化されてはじめてティーカフェ市場が確立していくのではないかと思います。
──将来的な目標をお伺いします。
角田 よく店舗数で聞かれますが、我々としてはファンをしっかり増やしていく中で、店舗が付いてくるものだと考えています。店の売上が高すぎると我々の目指すゴンチャ体験が提供できないので、売上が高すぎる店舗の近くにはもう1店舗開けるというのが基本的な考え方です。ニーズのあるところには出店していきます。そういう意味では、最終的には1000店舗くらいのボリュームを求められるブランドを作りたいという想いです。
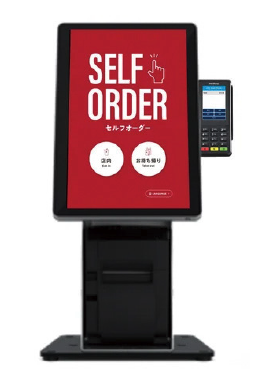
将来的には全店でキオスク端末を導入する予定
【ゴンチャ ジャパン】日本上陸10年で176店舗まで拡大(前編)
次なる成長を目指す
すべての経営者を応援する
フランチャイズ業界の専門情報誌

フランチャイズ業界唯一の専門情報誌として、毎号さまざまな切り口をもとに新興本部から大手本部までをフォーカス。またFCを自社の新たな経営戦略として位置付け、中長期的な経営を目指す経営層に向け、メガフランチャイジーの情報も提供しています。

次号発売のお知らせ
2025年4月22日発売
記事アクセスランキング
次なる成長を担うすべての起業家を応援する
起業&新規事業の専門情報誌

“起業のヒント” が毎号充実! “ビジネスチャンス” の宝庫です。
すぐにでも役立つ独業・開業・転業・副業サポートの雑誌です。
資金をかけずに始められる新しいビジネスの紹介、FC、経営・会社運営のノウハウなど、多くの経営者からの“起業のヒント”が毎号充実。



 人気のタグから探す
人気のタグから探す